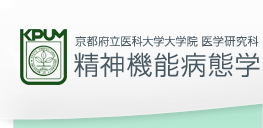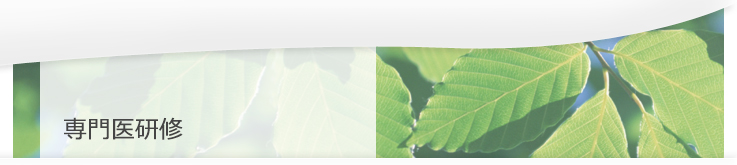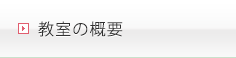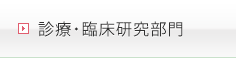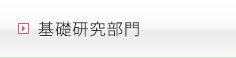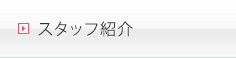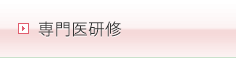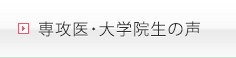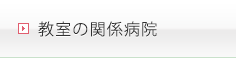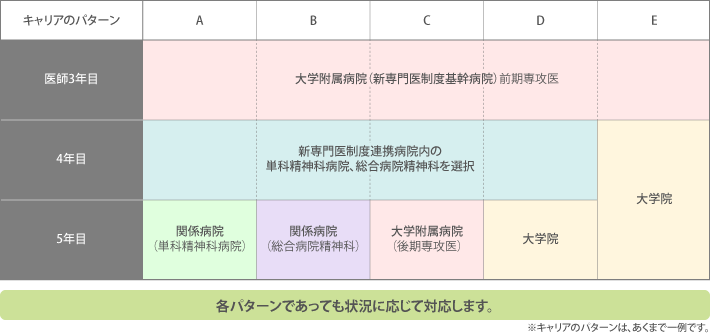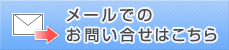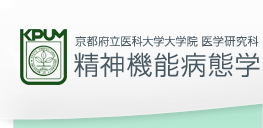
|
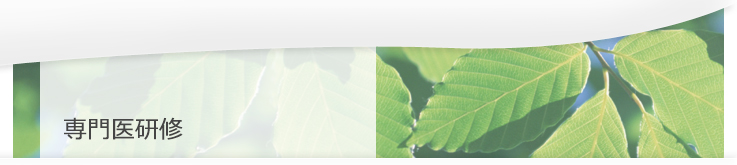
  専門医研修 専門医研修 |
今年で教室開講129年を迎えました。現在、教室は、成本教授のもと、准教授1、講師2、学内講師1、助教5、病院助教1、後期専攻医2、前期専攻医6、大学院生9、公認心理師2、精神保健福祉士1名で構成されています(令和6年4月1日現在)。
臨床、研究、教育のバランスを保ちながら、大学病院精神科としての役割を果たしています。平成30年度~令和6年度の入局者の内訳は、男性20名、女性8名です。出身大学別では、本学17名、他学11名です。教員や入局者に他大学出身者が多いのは、当教室の伝統的な特徴で、皆が出身大学に分け隔てなく従事しています。 |
京都府立医科大学は、大学附属病院として幅広い疾患に対応しており、統合失調症、気分障害に加えて、摂食障害、強迫性障害、認知症の入院治療を行っています。院内他科からの紹介によるリエゾン精神医療も行っています。外来は、思春期青年期、老年期、強迫性障害、認知療法といった専門外来を設置しています。年間を通してセミナーを行なっており、各精神疾患について、精神療法や各種治療法について、また精神保健福祉法や社会制度について知識と技能を獲得することが可能です。
専門医制度研修
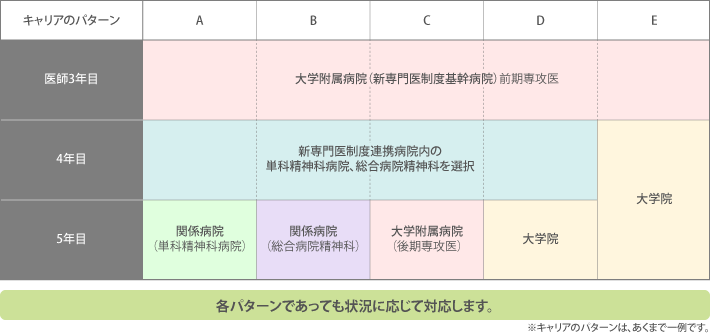
|
- 児童精神医学(京都府こども発達支援センター)やリワーク(復職)など産業メンタルヘルス分野の研修も可能です。
- 医師(専攻医)は当専門研修プログラムへの採用後、研修施設群のいずれかの施設と雇用契約を結ぶこととなります。
|
精神科急性期病棟:希望に応じて京都市内の単科精神科病院で研修が可能です。精神科リハビリテーション:希望に応じて京都市内の単科精神科病院、京都府精神保健福祉総合センターで精神科デイケアその他社会的リハビリテーションに関する研修が可能です。
認知症:希望に応じて京都市内の認知症治療病棟や老人保健施設で研修が可能です。
また、国立精神・神経医療研究センターで行われる精神保健に関する技術研修(発達障害・摂食障害・社会復帰リハビリテーションなど)や、肥前精神医療センター、久里浜医療センターで行われる認知症高齢者対策研修やアルコール・薬物に関する研修、うつ病や不安症に対する認知行動療法の研修などへの参加を積極的に支援しています。現在当教室に在籍するほとんどの専攻医がこれらのうち1つ以上の短期臨床研修に参加しています。
また、日本若手精神科医の会(JYPO)が主催するCourse for the Academic Development of Psychiatrists(CADP)にも毎年複数の大学院生・専攻医が参加し、各国の若手精神科医との国際交流を経験し、世界に発信できる基礎・臨床研究発表スキルを学んでいます。 |
大学における研修の内容

当科における前期専攻医・後期専攻医の研修の内容をご紹介します。 |
 外来陪席(予診を行った患者さんの本診察・再診に継続的に陪席) 外来陪席(予診を行った患者さんの本診察・再診に継続的に陪席)
 入院患者さんの担当(医員との複数担当制) 入院患者さんの担当(医員との複数担当制)
 関係病院での研修 関係病院での研修
 入退院カンファレンスでのプレゼンテーション 入退院カンファレンスでのプレゼンテーション
 担当指導医・各領域専門医による指導 担当指導医・各領域専門医による指導 |
| 年間を通じて実施される各種プログラムによって1年次から3年次まで充実した専門医研修をすることができます。下記の他に、他診療科と合同で行う臨床神経カンファレンス、脳神経内科・放射線科・精神科合同カンファレンス、集学的痛みセンターカンファレンスでの学習や発表を経験していただくこともできます。 |
| 大学の教員のみではなく、広く連携施設からもスペシャリストを招聘し、各精神疾患について、精神療法や各種治療法について、また精神保健福祉法や社会制度についてのセミナーを実施します。令和5年度の日程はこちらです。 |
| 連携病院で勤務する2,3年次専攻医(医師4年目、5年目)による症例報告会。1年次の大学病院での研修が終わってからも年に数回の症例報告会に参加していただき(発表は年に1回)、困っている症例のことなど相談に乗ることができます。 |
| 各年度終了時に精神科面接の達成度確認を行います。専門医試験における口頭試問に準じた形式で実施します。特に合否判定などはありませんが、形成的評価を行って研修の進捗を把握する機会にしていただきます。 |
| 1症例の半年~数年の精神療法・心理療法の経過を3時間ほどかけて検討します。専攻医の先生方には積極的に発表していただき、スペシャリストの先生方にスーパーバイズをしていただきます。
|
| 思春期の症例について精神療法だけではなく薬物療法・家族介入・精神保健福祉サービス調整など症例の介入について幅広く検討し、診療途中で経過が短い症例の検討も行います。症例検討だけではなく、思春期グループの勉強会を行うこともあります。 |
| リエゾンで経験した症例から派生して学習したことについて専攻医の先生方に発表をしていただきます。 |
| 日本精神神経学会専門医、精神保健指定医の取得を優先に考えています。並行して日本総合病院精神医学会・日本心身医学会・日本老年精神医学会・日本児童青年精神医学会(以上、研修施設として認定済み)の専門医・指導医等の資格取得も可能です。 |
臨床グループ
- 老年期グループ (認知症など)
- 思春期・青年期グループ (摂食障害など)
- 強迫症(強迫性障害)・神経画像グループ
基礎研究部門
- 行動・形態・薬理グループ
- コンサルテーション・リエゾングループ(リエゾン、緩和医療)
- 認知療法グループ
|
| 平成19年以降はイギリス・ロンドン大学セントジョージ校摂食障害部門、イギリス・ロンドン大学キングス校摂食障害臨床研究部門、カナダ・トロント大学老年精神医学部門、オランダ・アムステルダム大学アカデミック・メディカル・センター、オーストラリア・フリンダース大学など。 |
応募希望の方は、下記担当まで一度ご連絡下さい。随時ご説明します。
精神科研修を希望される他診療科勤務の方もご相談下さい。
専門医制度に関してお知りになりたい点などありましたら、お気軽にご相談下さい。 |
|
|